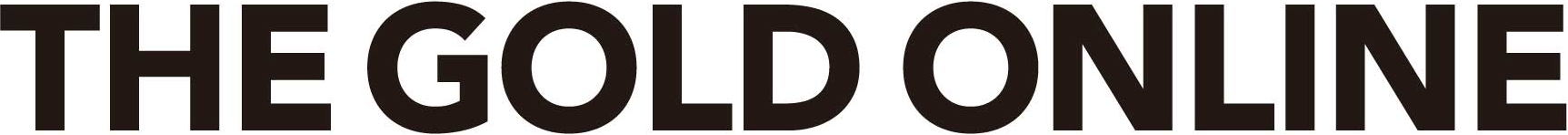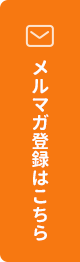60代のアパートオーナー、投資物件の「相続」で後悔しないためのポイント、3つ【弁護士が解説】

アパート経営では、万が一のときのために「相続」について考えておかなければなりません。アパートの相続の際、後悔することのないようにするためには、いくつかのポイントを押さえる必要がありますが、一体どのようなものでしょうか。本記事では、アパート経営の最終局面である「相続」について、法律事務所Zの溝口矢弁護士が解説します。
子どもたちのためのはずが…遺したアパートが相続争いの火種に
60代のアパートオーナーのAさんは、万が一のことがあった場合にも3人の子どもたち(配偶者は先に他界)が仲良く幸せに暮らしていけるよう財産を残したいと考え、堅実にアパート経営を行ってきました。経営するアパートの価値は4,500万円(ローン返済済み)。Aさんは、そのアパートの1室に長女と2人で暮らしていました。
そしてある日、心配していた「万が一」の事態が現実となり……Aさんは急病によって亡くなってしまいます。
Aさんのアパート以外の財産は、貯金が数百万円程度あるのみでした。Aさんは遺言書を遺していなかったため、3人の子どもたちは相続について話し合うことに。しかし、意見は対立してしまいました。
自分が住んでおり、生前両親が大切にしていたアパートを売りたくないと考える長女。Aさんの死亡をきっかけにアパートを売却して得たお金を平等に分配し、新たなスタートを切るべきだと考える2人の息子たち。
お互いに公平・平等な相続をすること自体に争いはないものの、方針について意見がまとまらず、結局は調停でも解決ができないまま裁判へ……。
Aさんの「子どもたちに仲良く幸せに暮らして欲しい」という願いとは裏腹に、激しい言い争いが繰り広げられることとなってしまいました。これではAさんは浮かばれません。
事例の反省点
Aさんはこのような子どもたちの争いを防ぐためになにができたでしょうか?
まず遺言書を作成し、Aさんの意思を示しておけば、少なくとも相続の方針そのもので大きな争いが生じることはなかったでしょう。大きなお金が関わると、どんなに関係が良好な家族間でもトラブルになり得ます。遺言書は被相続人であるAさんにしか作れませんから、事前に準備をしておくことが必要であったといえます。
加えて、信託契約(家族信託)の利用も検討する余地がありました。Aさんのケースでは財産のほとんどをアパートが占めており、子どもたちがアパートの共有を望まないことから、現状維持とするか、売却するかの二者択一を迫られるような状況になってしまいました。信託契約を締結していれば、こうした問題を防止できた可能性があります。
また、そもそも財産の大半をアパート1棟の価値が占めており、財産のバランスが偏っていることも問題であったと考えることができます。
たとえば、同じ4,500万円程度の相続財産でも、アパートの価値が1,000万円、預貯金が3,500万円であれば、アパートと預貯金のうち500万円を長女に、残る2人に預貯金1,500万円ずつを分配することができるでしょう。そうすることで、トラブルが生じることなく平等な相続を実現することができたかもしれません。このような意味では、財産のバランス(ポートフォリオ)の調整も重要であるといえます。
以下では、それぞれの対策についてポイントを説明していきます。
アパート経営における相続対策の3つのポイント
1.遺言書の作成
相続においては、被相続人(Aさん)の意思が尊重されます。そのため、遺言書が作成されている場合、相続人(3人の子ども)たちは、遺言書に示された被相続人の意思にしたがった相続を受け入れざるを得ません。
以下の対策と併せて総合的に被相続人として適切と考える相続の方法を、弁護士・税理士等の専門家のサポートを受けて検討することをおすすめします。
なお、いくら被相続人の意思が尊重されるといっても、各相続人には最低限の財産を渡さなければなりません(遺留分)。これを渡さなかった場合には、相続に不満のある相続人がほかの相続人に遺留分侵害額請求をし、トラブルになってしまう場合があるので注意が必要です。このようなことがないようにするためにも専門家のアドバイスを受けることは有用です。
2.信託契約(家族信託)の利用
不動産に関し、信託契約を締結することによって、委託者(Aさん)が死亡した場合だけでなく、認知症になるなどして意思を示すことが困難になった場合にも、安定して受託者(Aさんの代わりに不動産の管理等を行う者)が不動産および家賃収入を管理し、得た利益を受益者に分配することができます。そして、信託契約で定められた地位は相続可能です。
信託契約の受託者を信頼できる専門家や相続人のひとり(たとえばAさんの長女。このような場合を「家族信託」といいます)とすれば、Aさんの事例のような問題は生じなかったかもしれません。
信託契約は、法律関係が複雑であるため、遺言書の作成以上に慎重に対応する必要があります。銀行や専門家に依頼して行うことをおすすめいたします。
3.財産のバランス(ポートフォリオ)の調整
不動産は、金銭や株式と違って、相続人のあいだでわけることが容易ではない財産です(実質的にみて、単純な共有をすることが適切でないケースが少なくないため)。そのため、不動産が相続財産に含まれていても、ほかの財産とあわせて問題なく売却できるようなバランスにしておくことが理想的です。
資産形成はいろいろな要素が絡み合ってなされるものであるため、バランスのとれた財産状況とすること(綺麗なポートフォリオを組むこと)が難しいのは間違いありません。
もっとも、ある程度の段階で分配のしやすい財産状況にしておくことができれば、相続を柔軟に行うことが可能となり、トラブルが生じにくくなりますし、。遺言書の作成等もしやすくなるでしょう。
ある程度の年齢・段階になった時点で、資産形成から資産防衛・継承への移行の意識をもって、不動産投資の方針をより堅実なものとしたり、財産の調整をしたりして、バランスをとれるとよろしいでしょう。
個々の状況に合わせた適切な相続対策を
今回は、アパートオーナーの皆様に向けて相続対策について説明を行いました。
具体的にどのような対策をするか(遺言書や信託契約の内容、ポートフォリオの組み方)は、個々の状況によってさまざまです。資産に関する継続的な相談を銀行に行う、法的な問題について専門家のサポートを受けるなどしながら、安心して相続ができるような体制を整えていただけますと幸いです。
関連記事
サイトについて
アパート経営オンラインは、堅実・健全な不動産賃貸経営業をナビゲートする情報メディアを目指し、既に不動産を経営されている方、初めて行う方に向けてお届けするサイトです。
様々なことに向き合い、改善するきっかけとなりますようアパート経営オンラインでは、成功事例や失敗事例を交え、正しい不動産の経営方法をお伝えいたします。