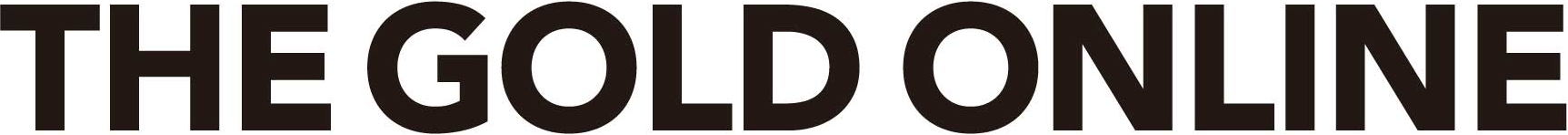老後の安心も円滑な相続も叶える…不動産オーナーのリスクヘッジを盤石にする「家族信託」×「資産管理法人」の強み【司法書士が解説】

長年にわたり不動産賃貸業を営むオーナーにとって、収益物件は安定収入の柱である一方、自身の認知症や相続への不安は尽きません。その備えとして有効なのが「家族信託」です。特に資産管理法人と組み合わせることで、万一認知症になっても会社の経営を止めず、株式という形で経営権をスムーズに次世代へ承継できるなど、より盤石なリスク対策が実現します。本記事では、賃貸不動産の相続における家族信託を活用した現実的な戦略を、実際の事例を交えて不動産相続の最前線で活躍する司法書士の近藤崇氏が解説します。
不動産の承継に役立つ「家族信託」
「家族信託」とは、財産を所有する人(委託者)が、親族(受託者)に財産の管理・運用・処分を任せる仕組みです。認知症対策や柔軟な承継計画に活用できる「次世代型の財産管理手法」として注目されています。
以下のような場面で、家族信託はとても有効な対策となります。
・認知症を発症した
……不動産の名義変更をせずに賃貸経営を継続できます。物件売却時に認知症を発症していても売却契約を締結することが可能です。
・老人ホームなどに入所した
……家賃収入を本人の生活費や医療費に充てることができます。
以下に具体的な事例を何点かあげ、その活用方法を検討してみましょう。
事例1.「家族信託」+「任意後見契約」のW使いで認知症リスクを回避
77歳のAさんは、老後の一人暮らしが心配になり、将来的な施設入所も視野に入れていました。しかし、認知症になってしまうと、賃貸不動産の売却や預金の引き出しも困難になるリスクがあります。
今後の一人暮らしと認知症リスクが心配になったAさんは、Aさんの長女が受託者となって、自宅と預貯金の一部を信託財産とする「家族信託」を導入することにしました。さらに念を入れ、本人の判断能力が落ちた段階で効力が発生する「任意後見契約」をAさんと長女とのあいだで行うことに。
こうすることで、仮にAさんが認知症を発症し、契約行為ができなくなってしまったとしても、家族信託を設定した財産はAさんの財産からの分離管理がなされています。さらに、それ以外の財産(=家族信託に含めていない財産)については任意後見契約を発動し、任意後見監督人の選任を受けた任意後見人が管理することが可能です。
このように制度を二重で用いることで、Aさんは財産が漏れることのない柔軟かつ安全な管理体制が整いました。
家族信託は、「資産管理法人」の承継にも役立つ
不動産の所有や管理のために、「資産管理法人」を設立している方も多いでしょう。家族信託は、個人所有の場合のみならず、こうした資産管理法人の「経営権」や「株式」の承継にも活用することができます。
不動産を資産管理法人名義で保有している場合、多くはオーナーの「1人株主」というケースが多いのではないでしょうか。
法人の代表者が認知症になると、原則、銀行取引や契約行為が一切できなくなります。さらに、1人株主である場合は、株主としての議決権も行使できなくなるため、潜在的に大きなリスクとなります。
この点、家族信託により、資産管理法人の株式の議決権を信託しておけば、あらかじめ定めた受託者が経営や株主総会での議決権を行使できるため、認知症などになった場合でも会社運営を妨げることはありません。
また、詳細の説明は省きますが、議決権のみを信託する場合、株式の配当などの経済的価値は引き続き委託者に属します。したがって、委託者はこうした配当などの経済的利益をそのまま享受できるだけでなく、株式としての経済的価値の移転を伴わないため、贈与税を課税されるリスクがまずないとされています。
さらに、受託者に議決権のみを与えることで、「(受託者に)勝手に株式を売却される」といったリスクも排除することができます。
遺産分割で揉めるリスクも最小限に
会社の株式は、非上場会社の株式であっても「相続財産」となります。そのため、相続人間で株式数が分割されている場合、どの株主も株主総会での必要十分な議決権に必要な株式数を確保できず、意見がわかれるなどしてともすると経営が機能不全に陥る可能性があります。
しかし、あらかじめ信託終了時の帰属先についても、株式の議決権の承継先を指定しておくことで、スムーズな次世代への承継が可能になります。
家族信託は「合意形成」と「信託監督人の配置」がカギ
家族信託は自由度が高い一方で、成年後見制度などと違い家庭裁判所や後見監督人からのチェックを受ける機会が少ないため、なにか問題があっても表面化する機会がない傾向にあります。そのため、家族間の合意形成と、第三者による監視体制が非常に重要です。
家族信託は、委託者の子どもが当初の受託者になるケースが大半ですが、この子どもと親の関係性、また子ども同士の関係性によっても使い分けをする必要があります。
事例2.親子間・きょうだい間の関係性が良好な場合
80代のBさんには、2人の子ども(長男・長女)がいます。Bさんと子どもたち、また子ども同士の関係性が比較的良好だったことから、Bさんは次のようなスキームで家族信託を導入しました。
・Bさんが委託者兼受益者
・長男が当初の受託者
・長女については信託監督人および受益者代理人として設定。収益アパートなど重要財産の処分については、受益者代理人である長女の同意を必須とする。
・Bさん死亡後、残余財産は2人が平等に取得する。
Bさんの信託の目的は、いずれ訪れるであろう施設入所や介護に備えた資金確保と、その際に柔軟に不動産の処分ができるようにすることです。
このため、親族内で役割を分担し、一定の形で子ども同士が緩やかに監視をする形式の家族信託を採用しました。
子どもとの関係性が悪い場合は、むりに家族信託を使わないという手も
一方で、もし親子間・きょうだい間の関係性が悪い場合には、家族信託の設計にも注意が必要です。この場合、同じ家族構成だとしても、上記のような家族信託の形が最適だとはいえません。Cさんの事例でみていきます。
80代のCさんにも、2人の子ども(長女・長男)がいます。長女はCさんの面倒をよく看てくれる一方で、長男はCさんの介護などにいっさい関与せず疎遠という状態です。Cさんは、「財産はなるべく長女に渡したい」と考えています。
この場合、家族信託などの仕組みは避け、1つ目の事例で述べた「任意後見契約」を長女と結び、かつCさんが「全財産を長女にのこす」という旨の公正証書遺言を作成する、という組み合わせで対処することが現実的かもしれません。
さらにいえば、長男から仮に遺留分請求があった場合に備え、金銭財産の一部については死亡時一時払いの生命保険を活用するといいでしょう。この生命保険については、相続税の対策にもなるため一石二鳥ともいえます。
ただし、家族信託を設計しない分、仮にCさんが施設入居費用を工面するために不動産を売却しなければならないという局面で、Cさんが重度の認知症を発症していた場合においては、前述の「任意後見契約」を発動する必要があります。
この点はデメリットといえるかもしれませんが、しかしこのケースにおいては、家族信託を“あえて使わない”ほうが適している可能性があります。
資産管理法人の承継も、個人不動産も“ハイブリッド”に備える
家族信託や資産管理法人の活用は、不動産賃貸業を営むオーナーが直面する「認知症リスク」や「相続問題」といった不安を、事前に解消できる強力な手段です。
とりわけ両者を組み合わせたハイブリッドな戦略は、さまざまな面で柔軟性が高く、会社事業と資産を確実に次世代へバトンタッチするための有効な選択肢となります。
ご家族の状況に応じた設計が重要となるため、まずは専門家に相談しながら、いまできる備えを1歩ずつ進めてみてはいかがでしょうか。
その際、忘れてはならないのが、家族以外の関係者の存在です。預金や融資取引のある銀行、収益アパートの管理会社など、事業に密接に関わる第三者に対して、事前の相談や、実際に制度を使って資産を動かす際の説明がしっかり行えるよう準備することも大切です。
関連記事
サイトについて
アパート経営オンラインは、堅実・健全な不動産賃貸経営業をナビゲートする情報メディアを目指し、既に不動産を経営されている方、初めて行う方に向けてお届けするサイトです。
様々なことに向き合い、改善するきっかけとなりますようアパート経営オンラインでは、成功事例や失敗事例を交え、正しい不動産の経営方法をお伝えいたします。