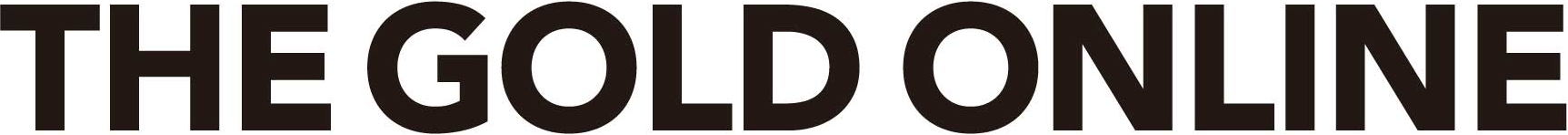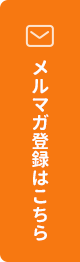築35年の「旧耐震アパート」、問題点とオーナーの責任範囲を弁護士が解説

地震が起きる度、所有している物件が倒壊しないか心配しているアパートオーナーもいるのではないでしょうか。対策を怠り、地震で倒壊した場合はオーナーが賠償責任を問われる場合もあります。本記事では、「新耐震基準」と「旧耐震基準」でわけられる耐震基準の違いとともに、旧耐震アパートの問題点やオーナーが負う責任範囲について柿沼彰弁護士が解説します。
地震でアパートが倒壊し、オーナーが賠償責任を問われた判例
アパートオーナーは、賃貸人として、賃借人に対して、安全なアパートを使用収益させる責任を負います(契約責任、民法601条等)。また、アパートは土地の工作物にあたるため、アパートに瑕疵がある場合には、オーナーは、その所有者として、被害者に対する損害賠償責任を負う場合があります(工作物責任、民法717条但し書)。
地震でアパートの賃借人4人が死亡…オーナーに「1億3,000万円」の賠償請求
地震でアパートが倒壊し、オーナーが、賃貸人に対して損害賠償責任を負うこととなった裁判例として、神戸地裁の平成11年9月20日判決があります。
この裁判例では、昭和39年築のアパートが、平成7年の阪神・淡路大震災(震度7)によって倒壊したことにより、アパートの1階に居住していた賃借人4人が死亡したことについて、オーナーに合計約1億3,000万円の損害賠償責任が認められました。
同裁判例では、契約責任と工作物責任は競合(被害者はどちらも自由に請求できるものの、同時に双方が認められての二重取りはできないことをいいます)するとして、アパートには、昭和39年の建築当時の安全基準を満たさない瑕疵があるのだから工作物責任が認められることを前提に、契約責任については判断されませんでした。
そして、建築当時の安全基準を満たしていたとしても震度7には耐えられなかっただろうものの、基準を満たしていれば被害を小さくすることはできたとして、生じた損害の50%について、オーナーの責任を認めました。
「新耐震基準」と「旧耐震基準」の違い
建築基準法により、アパートを含む建築物は、同法が定める基準を満たす必要があります。そのなかでも、耐震基準は、昭和56年6月1日以降に内容が大きく変更されました。
震度5がひとつの目安だった「旧耐震基準」
昭和56年5月31日までに建築確認を受けた建築物に適用されていた基準を旧耐震基準といい、旧耐震基準では、「中地震(震度5程度)で損傷しない」ことの検討が行われていました。その背景には、建築物が使われているあいだに何回か発生する中地震でも損傷しないならば、大地震(震度7以上)にも耐えられるという当時の見込みがありました。
しかし、昭和53年6月12日に発生した1978年宮城県沖地震では、震度5の地震であったにもかかわらず、28人の命が失われ、1,000棟以上の住宅が全壊しました。
目安が震度6強~7に変更となった新耐震基準
1978年宮城県沖地震を受けて、昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建築物からは、新たな耐震基準が適用されるようになりました。これを新耐震基準といいます。新耐震基準では、人命の確保が最優先とされ、大地震でも倒壊しないことの検討が行われるようになりました。
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、震度7が記録される大地震となりました。同震災では、旧耐震基準の住宅の約3分の2が大破および中・小破の被害を受けたとされる一方で、新耐震基準の住宅の大破および中・小破は約4分の1にとどまったといわれています。このように、旧耐震基準から新耐震基準への内容の変更は、実際に建築物の安全性に大きく影響しているといえます。
旧耐震アパートの問題点
旧耐震基準が適用されたアパートの建築物としての問題点は、地震に弱いことにつきます。もっとも建築基準法3条では、下記のとおり定めています。
・現に存する建築物に法令の規定に適合しない部分がある場合には、当該建築物に対しては、当該規定を適用しない
・当該建築物が、法改正以前の規定に違反している場合には、適用しない
やや複雑ですが、要約すると、基準が変わっても、過去の基準に適合していた建築物は違法にはならない、ということです。
現在の基準には適合しないが、建築当時の基準には適合している建築物のことを、「既存不適格」といいます。
旧耐震アパートを所有するオーナーが負う責任範囲とは?
先にご紹介した神戸地裁平成11年9月20日判決でも、この考え方を前提に、昭和39年建築のアパートについて、建築当時の基準に適合しているかどうかを判断し、適合しないから責任を負う、と結論づけています。この裁判例におけるアパートは、既存不適格ですらなかったため、アパートオーナーは責任を負うことになりました。
阪神・淡路大震災や、平成23年3月11日の東日本大震災を受けて、旧耐震アパートの住人が、オーナーに対して、新耐震基準を満たすように耐震補強工事をすることを求める訴訟を提起することが増えましたが、建築基準法の考え方に基づけば、請求は認められないことになります。
注意しなければならないのは、「アパートは老朽化する」ということです。旧耐震アパートは、新耐震アパートよりも長い時を経過しているのですから、老朽化が進んでいることが通常です。オーナーには、新耐震基準を満たす必要はなくとも、通常の使用に必要な程度の修繕はする義務があります(民法606条1項本文)。
オーナーはアパートを安全に使用収益させる責任を負う
旧耐震アパートは新耐震基準に適合しておらず、新しいアパートに比べて地震に弱いことが通常です。もっとも、建築基準法では、「旧耐震アパートが、建築当時の耐震基準に適合していれば、既存不適格として違法ではない」としています。そのため、オーナーは、旧耐震アパートが、新耐震基準に適合するように補強工事を行う責任を負うものではありません。
しかし、アパートのオーナーは、アパートの安全を維持して、賃借人に安全に使用収益※させて、通行人等にも被害を与えないようにする責任を負っています。そして、旧耐震のアパートは老朽化が進んでいることが通常であり、新耐震基準を満たさないだけでなく、通常使用するための安全性すら備えていないことがよくあります。
※私法上の概念で、ものを直接に利活用して利益・利便を得ることをいう
このような場合には、オーナーは、アパートを修繕して、賃借人に安全に使用収益させて、通行人等にも被害がおよばないようにする責任を負うことに、注意する必要があります。
関連記事
サイトについて
アパート経営オンラインは、堅実・健全な不動産賃貸経営業をナビゲートする情報メディアを目指し、既に不動産を経営されている方、初めて行う方に向けてお届けするサイトです。
様々なことに向き合い、改善するきっかけとなりますようアパート経営オンラインでは、成功事例や失敗事例を交え、正しい不動産の経営方法をお伝えいたします。